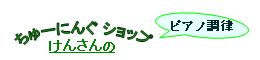ピアノ調律技術 トップ →ピアノ技術 整調 → ハンマーストップ
ハンマーストップ
機能
ハンマーは当然のこと、打弦後にストップが無ければ暴れます。ハンマーレールに跳ね返って、予期せぬ連打もしてしまうでしょう。関連工程
主に影響を受けるのは、あがき。厳密にはカラや接近の影響を受けるかもしれない。寸法
狭い:連打性能広い:低速連打反応性能
タッチによってストップ位置は変化し、その変化具合もピアノによって全く違います。ピアノの固体差を観察し、目的の性能を考慮した寸法を考えなければいけません。ピアノの固体差を観察せずに狭くしすぎると、整調時は大丈夫でもタッチによってはストップが弦振動に影響することもあります。狭いと経年変化による機能不全の危険性も増します
構造
ストップを広くすることによる反応性能向上は、ハンマーレールクッションの材質に大きく依存します。昔ながらの素材に拘らず、より跳ね返りを抑えた物質を使えば、ストップを広くする意味も薄れます。
ヤマハの場合、木に突き刺さった金属を無理に曲げて調節する方法なので、整調することによって内部応力を作り、経年変化に悪影響を及ぼすとも考えられます。部品自体も傷んでいくので、見た目に拘ってキッチリ揃えるくらいなら、触らない方が良いのではないでしょうか。
その他
UPはGPよりバックチェックワイヤーが長い(回転中心の影響;回転円接線軸とワイヤー軸の関係もあるが)ので、タッチによる寸法変化が起き易い。だがGPの場合、ワイヤーが短いからバックチェック角度の影響がシビアになる。木+フェルトという材料の影響などもあるし、雑音を考慮する必要がある。