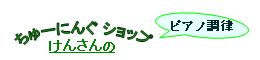ピアノ調律技術 トップ →ピアノ技術 設計 → バットスプリング
UP_バットスプリング
ヤマハピアノを見たところ、燐青銅ではなくステンレス鋼へ移行した方が良いのでは?ということで色々考えていきます。現状
UPで弱打をする場合、どんなに働きが正常であっても2度打ちする事が多々あります。ハンマーシャンクの長さが、他とは異なる低音下側の最弱打では、2度打ちしないピアノは無いくらいです。それはバットsprのへたりが根本的な原因です。 バットsprは取付いた状態で約20°の角度となります。
バットsprは取付いた状態で約20°の角度となります。 ばね開放状態では、新品で約140°である為、ばねの変位角(捻られた角度)は120°程になります。
ばね開放状態では、新品で約140°である為、ばねの変位角(捻られた角度)は120°程になります。 約1年後には開放状態で90°くらいまでへたります。変位角は70°程になり、ばねとしての力は2/3くらいに落ちます。
約1年後には開放状態で90°くらいまでへたります。変位角は70°程になり、ばねとしての力は2/3くらいに落ちます。 約2年後には開放状態で80°くらいまでへたり、以降この状態で安定します。変位角は60°程となり、新品時の半分くらいの機能しかありません。
約2年後には開放状態で80°くらいまでへたり、以降この状態で安定します。変位角は60°程となり、新品時の半分くらいの機能しかありません。物性値
バットsprの力の簡易比例式:(縦弾性係数*円周率*線径の4条*変位角)/バネ部全長・・・φ=64M{πDN+(a1+a2)/3}/Eπd^4より・・・縦弾性係数[GPa]
●燐青銅:98
●ステンレス鋼:190
つまり、同寸法でステンレス鋼では約2倍の力になる。現状のへたった状態の寸法で作り上げれば、新品と同等の性能を持つステンレス鋼sprになる。
耐へたりの参考値となる引張強さ[N/mm^2]
●燐青銅:345~935
●ステンレス鋼:1600~2100
成型後の処理によりバネ性能は左右されますが、基本的な機械的材料性能には2倍以上の差があります。
ステンレス鋼を選ぶ理由
銅合金である真鍮・青銅は安価で歴史も古いが、近年の他分野ではステンレス鋼に代えていってる流れもあり、信頼できる材料変換と思われる。厳密には、ハンマー位置とバネ応力の関係は現状とは変わりますが、特に現状の完全再現は必要ないでしょう。むしろ非線形バネへ改良すべきです。ステンレス鋼以外の可能性
なぜピアノは銅合金に拘るのか?銅合金である必要があるならば、ベリリウム銅の方が機械的性能は高く、ばね限界値(ばねに掛かる力を取り除いた時、ばねが元の形に戻ることができる最大荷重)も2倍ほどはあります。絶対に燐青銅である必要があるとしても、寸法設計を見直すことにより改善することもできると思われます。
??ヤマハ??
バネは、成型後、耐へたりや性能安定の為に様々な後処理を行います。その内の一つとしてセッティングがあります。バネに用途以上の力を加えて最終的な製品寸法にし、内部にはへたりとは反対方向の残留応力を残して仕上げられます。
ヤマハ製品を私見で感じただけですが、ピアノを製造して販売されるまでの性能に的を絞っていて、セッティングも行ってないように見受けられます。
バネは、成型後、耐へたりや性能安定の為に様々な後処理を行います。その内の一つとしてセッティングがあります。バネに用途以上の力を加えて最終的な製品寸法にし、内部にはへたりとは反対方向の残留応力を残して仕上げられます。
ヤマハ製品を私見で感じただけですが、ピアノを製造して販売されるまでの性能に的を絞っていて、セッティングも行ってないように見受けられます。
計算
ばね線径0.5mm/巻数3/コイル径1.5mm/腕長25+5mm通常角0.47rad/打弦時0.4rad
ばね定数[N・mm/rad]=Eπ0.54/64(4.5π+10)
りん青銅E=98000[MPa]より、ばね定数は12.456。
応力の変化量は、12.456*0.07*(32/π0.53)=70MPa
りん青銅引張り強度345~930MPa(500で計算)、
最大応力500*0.6=300MPa以下にする必要があるので、逆算して
最大モーメントは300*(π0.53/32)=3.7N・mm
変位角は3.7/12.456=0.3rad
解放ばね角は0.3+0.4=0.7rad(40°くらい)
最高級りん青銅では、6.8N・mm_0.95rad(55°くらい)
設計図も無く推測で計算しただけであるが、ヤマハ新品140°はとても正気の設計とは思えない。以上は疲労限度から寸法を考えたが、次に新品を付けた瞬間の塑性変形を考える。
高級りん青銅の弾性限度を750MPaとし、
モーメントは750*(π0.53/32)=9.2N・mm
変位角は9.2/12.456=0.74rad(40°くらい)
仮定値誤差・ばね後処理・実物の変形具合を考慮すると、計算値の+2,30°くらいが必要かとも思える。